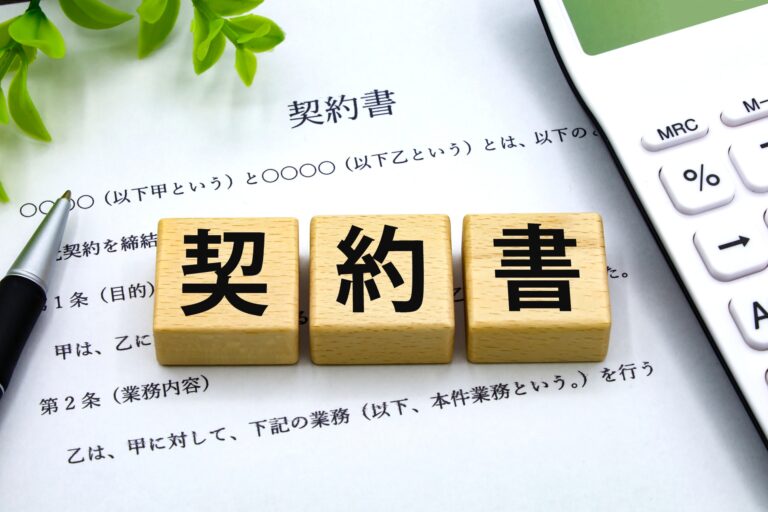「リースバック契約書」とは、自宅などの不動産を売却したあとも、元の持ち主が賃貸契約を結んで住み続けられる「リースバック」の仕組みにおいて、売主と買主(=貸主)が交わす正式な契約書です。
契約書には、売買の詳細はもちろん、家賃や契約期間、再契約や退去の条件までが記載されており、不十分な理解でサインしてしまうと、のちのトラブルに繋がる可能性もあります。
この記事では、リースバック契約書の具体的な内容と注意点、トラブル事例や事前に確認すべきポイントを詳しく解説します。
目次
リースバックとは?
リースバックは、所有する不動産を不動産会社などに売却し、売却代金を得たうえで、そのまま賃貸契約を結び、自宅に住み続けることができる仕組みです。
売却と賃貸が同時に行われるため、「売っても住み続けたい」という希望を叶える選択肢として利用されています。
リースバックは、具体的に以下のようなシーンで選択されます。
- 老後資金の確保
- 住宅ローンの返済
- 事業資金の調達
- 相続対策や離婚時の財産分割
住宅を手放すことなく資金を得られる点が、リースバック最大のメリットです。
リースバック契約書に記載される主な内容
リースバックでは、以下の2種類の契約書を締結します。
売買契約に関する条項
- 売却価格
- 所有権移転の時期
- 買主と売主の役割分担(登記費用・税金など)
売買契約は、物件の所有権を正式に移転するための重要な契約です。
賃貸借契約に関する条項
- 家賃(月額いくら)
- 契約期間(通常2年、更新の有無)
- 敷金・礼金・更新料の有無
- 使用目的と居住人数の制限
契約書の中でもっとも注目すべきは、この賃貸部分です。
契約終了時の対応
- 明け渡しの時期と条件
- 原状回復義務の有無
- 再購入オプション(買い戻し)に関する条項
再購入が可能かどうかは、契約書で明確にされている必要があります。
契約書で必ず確認すべき6つのポイント
リースバックの契約は一般的な不動産売買契約と賃貸借契約を組み合わせた複雑なものです。
後で「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、契約書にサインする前に、特に以下の6つのポイントを徹底的に確認しましょう。
1. 家賃の金額と見直しの有無
家賃は、周辺相場や売却価格に応じて設定されますが、更新時に家賃が変更されるかどうかは事前に確認が必要です。
2. 契約期間と再契約の条件
最も重要なのは「再契約ができるのかどうか」です。
貸主(リースバック会社など)が再契約を拒否できる条件(家賃滞納以外にも、物件の老朽化、貸主の都合など)が明記されていないか、また、再契約時に家賃やその他の条件が見直される可能性があるかを確認しまする必要があります。
場合によっては、更新が一切できない「定期借家契約」となるケースもあるため、注意が必要です。
3. 途中解約の可否・違約金の有無
契約は一度締結すると拘束力が発生します。
しかし、予期せぬ事情で契約期間中に引っ越す必要が出たり、あるいは貸主側が契約を早期に終了させたいと考えたりする可能性もゼロではありません。
そのため、途中解約に関する条項は必ず確認すべきです。
- 借主側からの解約条件:
転勤や病気など、やむを得ない事情で借主(あなた)から契約を中途解約できる条件や、その際の事前通知期間(例:〇ヶ月前までに通知)を確認します。 - 貸主側からの解約条件:
貸主(リースバック会社など)が契約期間中に一方的に解約できる条件(例:大規模修繕が必要になった場合、売却を決定した場合など)が明記されていないか、また、その際に借主への補償(引越し費用など)があるかを確認します。 - 違約金の有無と金額:
契約を途中解約する際に、違約金や損害賠償が発生するかどうか、そしてその金額や計算方法が明確に記載されているかをチェックしましょう。
4. 再購入(買い戻し)の条項
「今は売却せざるを得ないが、将来的に経済状況が回復したら、もう一度この家を買い戻したい」と考えている方もいるでしょう。
その希望がある場合、再購入(買い戻し)に関する条項が契約書に盛り込まれているかを必ず確認してください。
- 買い戻し権の有無:
そもそも買い戻しが可能かどうかが明記されているか。買い戻しを保証する「買戻特約」が登記されるケースもありますが、口約束は危険です。 - 再購入価格:
買い戻す際の価格が、売却価格と同額なのか、あるいは将来の市場価格や一定の利率を上乗せした価格になるのかを確認します。具体的な価格設定方法が明記されていることが重要です。 - 買い戻しの期間と条件:
いつからいつまでの期間に買い戻しができるのか、また、どのような条件(例:家賃滞納がないこと、現金一括での購入など)を満たせば買い戻せるのかを明確にしておきましょう。 - 優先購入権:
他の購入希望者が現れた場合でも、あなたが優先的に購入できる権利があるかどうかも確認ポイントです。
5. 原状回復の範囲
賃貸借契約を結ぶ上で、退去時の原状回復に関する取り決めは非常に重要です。
売却前に住んでいた家とはいえ、賃貸として借りる以上、通常の賃貸物件と同様に、退去時の修繕やクリーニングの費用負担が発生する可能性があります。
- 原状回復の定義:
どこまでの範囲が原状回復義務の対象となるのかを確認します。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、一般的な損耗や経年劣化は貸主負担となるのが原則です。 - 借主負担となる具体的な範囲:
故意や過失による損傷、善管注意義務違反による汚れなど、借主負担となるケースが具体的に明記されているかを確認しましょう。 - ハウスクリーニング費用:
退去時のハウスクリーニング費用が借主負担となるか、その場合の費用概算なども確認しておくと安心です。
6. 退去時のサポート内容
引越し費用の補助や、提携する不動産会社の斡旋サポートがついているケースもあります。
リースバック契約でよくあるトラブルとその回避策
リースバック契約のよくあるトラブルとして、以下のような事例が挙げられます。
1. 早期に退去を求められる
リースバック契約でよくあるトラブルの一つが、「思ったよりも早く家を退去することになった」というケースです。
これは、主に賃貸契約期間が極端に短かったり、契約更新が保証されていなかったりする契約が原因で発生します。
例えば、契約期間が1年や2年と短く設定されており、貸主側がその後の更新を拒否する可能性がある場合、住み続ける計画が崩れてしまいます。
回避策
契約締結前に、必ず契約期間の長さ(最低でも3年以上が望ましい)と、契約期間終了後の再契約の条件を徹底的に確認しましょう。
可能であれば、自動更新の条項がある契約や、更新拒否事由が明確に限定されている契約を選ぶことが重要です。
口頭での説明だけでなく、契約書に明記されているかを必ず確認してください。
2. 家賃が突然上がる・更新拒否される
リースバック契約におけるもう一つの大きなトラブルは、契約更新時に家賃が大幅に上がったり、貸主側から更新を拒否されたりすることです。
契約書に家賃の見直しルールや更新条件が曖昧にしか書かれていないと、貸主の都合で一方的に家賃を吊り上げられたり、住み続けることができなくなったりするリスクが生じます。
回避策
契約更新時のリスクを避けるためには、以下の点を事前に確認しましょう。
- 家賃の見直しルール:
契約書に家賃の見直し時期(例:2年ごと)や、見直しの際の計算方法、上昇幅の上限などが具体的に明記されているか。 - 更新拒否の条件:
貸主が更新を拒否できる具体的な条件(例:家賃滞納、物件の著しい損耗など)が明確に記載されており、かつ妥当であるか。貸主の都合で安易に更新拒否できないようになっているかを確認することが重要ですし、定期借家契約でないかも確認すべきです
3. 買い戻しができなかった
「将来的には家を買い戻したい」と考えてリースバックを利用する方もいますが、実際に買い戻しができないというトラブルも少なくありません。
これは、契約書に再購入(買い戻し)に関する条項がなかったり、買い戻し価格が高すぎたりすることが主な原因です。
口頭での約束だけでは法的な効力がないため、トラブルに発展しやすいのです。
回避策
将来的に買い戻しを希望する場合は、以下の点を必ず契約書に盛り込むよう交渉しましょう。
- 再購入権(買戻特約)の明記:
契約書に買い戻しの権利が明確に記載されているか、さらには登記される「買戻特約」の有無も確認すべきです。 - 再購入価格と条件の明確化:
買い戻し時の価格(売却価格と同額か、上乗せがあるか)、買い戻し可能な期間、そしてその際の条件(例:現金一括購入、ローン利用の可否など)を具体的に契約書に明記することが不可欠です。あいまいな表現はトラブルの元となります。
契約書を交わす前にチェックすべきこと
リースバックでのトラブルを防ぐために、契約書を交わす前に以下の点をチェックしましょう。
①契約書のひな形・見本を確認
契約内容を深く理解するためには、実際に交わす契約書のひな形や見本を、契約締結よりも前に業者から取り寄せて、じっくりと読み込むことが非常に重要です。
初めて目にする専門用語や、意味が分かりにくい条項があれば、決して曖昧なままにせず、担当者に納得できるまで質問を繰り返しましょう。
質問への回答が不明瞭だったり、説明を避けるような業者であれば、契約を慎重に検討すべきサインかもしれません。
事前に確認することで、不明点を解消し、冷静な判断を下す準備ができます。
②専門家(弁護士・司法書士)による契約内容の確認
リースバック契約は、不動産売買と賃貸借が組み合わさった、法的にも複雑な契約です。
そのため、ご自身だけで内容を全て理解し、潜在的なリスクを見抜くのは困難を伴います。
不動産や契約法に強い弁護士や司法書士といった法律の専門家に、契約内容を事前に確認してもらうことを強くお勧めします。
専門家は、一般の方には分かりにくい不利な条項や、将来的なリスクにつながる可能性のある文言を見つけ出し、法的なアドバイスを提供してくれます。
専門家への依頼費用はかかりますが、後々のトラブルや損失を考えれば、これは非常に価値ある投資と言えるでしょう
③信頼できる業者かどうかの見極めポイント
リースバックの成功は、依頼する業者の信頼性に大きく左右されます。
複数の業者を比較検討し、本当に信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
- 実績・口コミ・紹介実績:
長年の実績があり、良い口コミや評判が多いか、弁護士や金融機関からの紹介実績があるかを確認しましょう。
過去の成功事例や、トラブルへの対応力を示す重要な指標となります。 - 無理な契約を急がせないか:
「今すぐ決めないと」「今日中にサインを」などと、契約を無理に急かしたり、考える時間を与えなかったりする業者には要注意です。
お客様の不安を煽り、冷静な判断を妨げようとする業者は避けるべきです。 - 契約書に不利な条項がないか:
家賃の急な値上げ、短期での契約解除、買い戻し条件が不明瞭、原状回復の範囲が過剰など、お客様にとって不利な条項がないかを丁寧に説明してくれるか、疑問点に誠実に対応してくれるかで、業者の信頼性を判断できます。
リースバック契約はこんな人におすすめ
リースバック契約は、「自宅を売却して現金を得たいけれど、住み慣れた家は離れたくない」というニーズに応える有効な手段です。
具体的には、以下のような状況の方に特におすすめできます。
- 老後の生活資金を確保したいが住み慣れた家を離れたくない方:
リタイア後の資金不安を解消しつつ、慣れ親しんだ住環境を維持できます。 - 離婚や相続で一時的に資産を分けたい方:
共有名義の不動産を売却し、現金を分ける必要があるが、一時的にどちらかが住み続けたい場合に活用できます。 - 住宅ローンを延滞していて任意売却を検討している方:
競売を回避しつつ、売却後も自宅に住み続けることで、生活基盤の急激な変化を避けられます。 - 事業資金が急に必要になったが、住居は変えたくない方:
自宅を売却して事業資金を捻出しながら、引き続き同じ場所で生活・事業を継続したい場合に適しています。
「売っても住み続けたい」というニーズを持つ方にとって、リースバックは資金調達と居住継続を両立させる、柔軟な解決策となるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. リースバック契約書はキャンセルできますか?
→ 契約前であればキャンセル可能です。契約後は、条件により解約手数料や違約金が発生する場合があります。
Q2. 家賃は途中で変更されますか?
→ 更新時に変更される可能性があります。契約書に「家賃見直しルール」があるか確認しましょう。
Q3. 契約更新を拒否されたらどうなりますか?
→ 原則、契約終了時に退去が求められます。長期契約や自動更新の契約を選んでリスクを減らしましょう。
Q4. 再購入は必ずできますか?
→ 再購入の条項が契約書に明記されていなければ、原則できません。価格・期限・条件などが契約書に記載されているか要確認です。
まとめ|リースバック契約書は納得してからサインを
リースバック契約書は、売買契約と賃貸契約の要素を併せ持ち、内容をよく理解せずに契約すると後悔するリスクがあります。
特に「家賃」「契約期間」「再購入の可否」は慎重に確認すべきポイントです。
不安があれば、必ず専門家に相談した上で契約しましょう。
信頼できる業者と、納得のいく契約を結ぶことが、リースバック成功の第一歩です。
センチュリー21中央プロパティーは、これまでに5,000件以上、住宅ローンの支払いで悩む方をサポートしてきた実績があります。
債務整理に強い常駐の社内弁護士が、競売を回避し、あなたに最適な解決策をご提案します。
住宅ローンでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。