夫婦が共同で購入したマイホームも、離婚時は頭を悩ませる大きな問題となります。
特に、ペアローンを利用している場合、名義の単独化か売却という二つの選択肢が現実的な対応策として存在します。
しかし、住宅ローンが残っている不動産は通常売却が難しいのが現状です。そこで、注目されるのが任意売却という解決方法です。
この記事では、“離婚後のペアローン”という複雑な状況下にある自宅の適切な対処法について、詳しく解説していきます。具体的には、任意売却を選択した場合の手続きの流れや、スムーズに解決するための重要なポイントなどを分かりやすくご紹介します。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
目次
離婚時に厄介なペアローン問題
離婚時に厄介なペアローン問題は、以下のようなものがあります。
- ローンの債務が残り、経済的な負担が増える
- 単独名義にした後の維持管理が大変
- 売却する際には、双方の同意が必要
- オーバーローンで売却できない
- 連帯保証が付きまとう
- 元配偶者と関係性が続くストレス
①ローンの債務が残り、経済的な負担が増える
離婚により世帯収入が減少するにも関わらず、双方それぞれが独立した債務者のためペアローンの返済義務は引き続き残ります。ペアローンは、一方が返済を滞納すると、連帯保証人であるもう一方に請求が来ますので、個人にかかる経済的負担が大幅に増加します。
また、どちらか一方が自宅を出て新たな住居を借りる場合、元の住宅ローンの返済に加えて二重に支払いも発生し、経済的な負担はさらに重くなります。
②単独名義に移転後の維持管理が大変
住宅をどちらか一方の単独名義にする場合、相手の持分を買い取る資金が必要になります。
また、ローンの名義(契約者)変更は容易ではなく、金融機関の審査をパスする必要があります。単独名義にした後も、固定資産税や修繕費といった維持管理費用全てを一人で負担することになり、経済的な負担が大きくなる可能性があります。
③売却する際には、双方の同意が必要
ペアローンで購入した不動産は夫婦の共有名義であることが一般的です。
そのため、売却するには原則として婚姻中であれ、離婚後であれ双方の同意が不可欠です。どちらか一方が売却に反対したり、いくらで売るかの価格で揉めたりすると、手続きが滞り、不動産を処分できずに問題を長期化させる原因となります。
④オーバーローンで売却できない
不動産の売却価格が住宅ローンの残債を下回る状態(オーバーローン)の場合、売却してもローンを完済できません。オーバーローンの場合、売却代金で完済できない不足分の資金をどう工面するか、で双方で意見がまとまらないケースが多いです。
⑤離婚後も付きまとう連帯保証
ペアローンでは、夫婦がお互いの連帯保証人となっていることが一般的です。
離婚してもこの連帯保証契約は原則として解除されません。もし元配偶者がローンの返済を滞納した場合、たとえ自分のローン返済に滞りがなくても、連帯保証人としてその返済義務を負うリスクが継続します。
⑥元配偶者と関係性が続くストレス
住宅ローンの返済、不動産の管理、売却手続きなど、離婚後も住宅に関する様々な問題について元配偶者と連絡を取り合い、共同で対応せざるを得ない状況が続きます。
これらの話し合いや手続きは、離婚をする夫婦にとって、予期せぬ大きなストレスになります。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
離婚に伴うペアローン問題の3つの選択肢
離婚に伴うペアローン問題では、以下の3つの選択肢があります。
- ペアローンを解消し1本化する
- 通常売却する:アンダーローンの場合
- 任意売却する:オーバーローンの場合
①ペアローンを解消し1本化する
双方のどちらか一方が家に住み続ける場合、残りの住宅ローンをその一人の名義にまとめ直す方法です。住み続ける側が単独の債務者(契約者)となり総額のローンを返済していくことになります。
ただし、金融機関の審査があり、単独での返済能力が十分と認められる必要があります。
また、単独名義にするということは、相手の持分を買い取ることになります。そのため、相手の持分を買い取るための資金や財産分与の手続きが必要になる場合もあります。
② 通常売却する:アンダーローンの場合
不動産の売却価格が住宅ローンの残債務を上回る「アンダーローン」の状態であれば、不動産を売却し、その代金でローンを完済する方法です。ローン完済後に手元に残ったお金は、夫婦で財産分与の手続きとして分けられます。
最も経済的な清算がしやすく、関係性を断ち切りやすい選択肢ですが、双方の売却への同意が必要です。
③ 任意売却する:オーバーローンの場合
先述の通り、不動産の売却価格が住宅ローンの残債務を下回る「オーバーローン」の状態の場合、通常売却ではローンを完済できません。そのため、オーバーローンの場合は、任意売却という手段を選択せざるを得ません。
任意売却では、債権者である金融機関の合意を得て、市場価格に近い価格で不動産を売却します。売却後もローン残債務は残りますが、競売よりも高く売却できる可能性があり、残った債務についても柔軟な返済交渉ができるメリットがあります。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
ペアローン離婚における任意売却の注意点
離婚に伴いペアローン返済中の不動産を任意売却するか考えた場合、、オーバーローンの場合に有効な選択肢ですが、いくつかの重要な注意点があります。以下に詳しく解説します。
夫婦間での合意形成が前提条件
任意売却は、夫婦共有名義の不動産を売却するため、夫婦双方の明確な同意が何よりも重要です。
売却価格、売却時期、不動産業者への仲介手数料などの諸費用、そして最も複雑なのは、売却後に残るローン残債の支払い義務やその方法について、離婚条件と合わせて事前に徹底的に話し合い、合意しておく必要があります。
合意形成が難しい場合は、弁護士や離婚問題に詳しい専門家を交えて話し合いを進めることも検討しましょう。
債権者(金融機関)との交渉が必要
任意売却は、住宅ローンの債権者である金融機関の同意なしには成立しません。売却価格は市場価格に基づきますが、債権者は少しでも多くローン残債を回収したいと考えているため、提示された売却価格について交渉が必要になる場合があります。
また、売却にかかる諸費用(仲介手数料など)を売却代金の中から支払うことについても、債権者の承諾が必要です。
これらの交渉は個人で行うのが難しいため、通常は任意売却の実績が豊富な不動産業者や弁護士に依頼し、金融機関との交渉を代行してもらうのが一般的です。
オーバーローンの場合:残債務の支払いや債務整理の検討
任意売却は基本的にオーバーローンの状況で行われるため、不動産を売却しても住宅ローンの残債務が残ります。この残った債務について、どのように返済していくかを債権者と話し合い、合意する必要があります。
通常は無理のない範囲での分割払いが認められることが多いですが、返済計画についてしっかりと交渉することが重要です。夫婦それぞれに残債の支払い義務が残るため、どちらがどの程度返済していくのか、夫婦間でも明確に取り決めが必要です。
残債務が多額で返済が困難な場合は、自己破産などの債務整理も選択肢として検討する必要が出てくるため、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
連帯債務・連帯保証人は解除できない可能性がある
ペアローンの場合、原則夫婦がお互いの連帯保証人となっています。任意売却が成立し、不動産を売却した後も、原則としてこの連帯保証の関係は自動的に解除されません。
売却でローンが完済できず残債務が残った場合、主債務者だけでなく連帯保証人もその残債務に対して返済義務を負い続けます。
連帯保証を解除するには、新たな保証人を立てるか、残債務を一括返済するなど、債権者が認める代替手段が必要であり、非常にハードルが高いのが現状です。
ペアローンは離婚後も元配偶者の残債務に責任を負うことを理解しておく必要があります。
住宅ローン控除の適用は受けられなくなる
住宅ローン控除は、マイホームの取得のために組んだ住宅ローンの年末残高に応じて所得税などから税額控除を受けられる制度です。
任意売却により住宅ローンを完済(または残債を支払い続けることになっても、居住用財産ではなくなるため)した場合、原則として売却を行った年以降は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
税金の計算や申告に影響するため、この点も事前に確認が必要です。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
離婚後に共有名義を続けるのが危険な理由
離婚後も、共有名義の不動産を所有し続けることは、将来的に様々なリスクを伴います。ここでは、特に注意すべき点を詳しく解説します。
不動産所有にかかる経済的負担:維持費のリスク
不動産を所有している限り、たとえ自身が住んでいなくても、年間を通じて様々な維持管理費用が発生します。代表的なものとして、固定資産税や都市計画税といった公租公課が毎年課税されます。
また、マンションであれば毎月の管理費や修繕積立金が必要ですし、戸建てでも定期的なメンテナンス費用がかかります。
特に共有名義の場合、これらの維持費は持分割合に応じて分担するのが一般的ですが、共有者のいずれかが支払いを滞納すると、もう一方の共有者がその不足分を肩代わりしなければならないリスクが生じます。想定外の経済的負担を避けるためにも、共有状態の解消を検討することが重要です。
自由な処分が困難:売却や活用における制約
共有名義で登記されている不動産を売却したい場合、原則として共有者全員の同意が必要です。これは、たとえ自身の持分割合が大きくても、あるいは相手の持分がわずかであっても変わりません。共有者のうち一人でも売却に反対すれば、その不動産を市場で売却することは事実上不可能となります。
離婚後に元配偶者と連絡を取り合う必要が生じるだけでなく、意見の対立から売却が進まず、不動産が「負動産」化してしまうケースも少なくありません。将来的な売却や有効活用を視野に入れるのであれば、共有状態の早期解消に向けた話し合いが不可欠です。
将来のトラブルの種:相続の複雑化
共有名義不動産の所有者のうち一人が亡くなると、その死亡した共有者の持分は、その人の法定相続人へ相続されます。もし亡くなった元配偶者が再婚していたり、前婚との間に子供がいたりする場合、見ず知らずの人が新たな共有者として加わる可能性があります。
世代を重ねるごとに共有者が増え、権利関係が複雑化していくと、ますますその不動産の売却や管理に関する合意形成が困難になります。最悪の場合、誰が所有者なのかさえ分からなくなる「所有者不明土地問題」が表面化し、将来の子や孫の世代にまで面倒やトラブルを引き継がせてしまうリスクがあります。
滞納による最悪の事態:差し押さえと競売
ペアローンでは、夫婦それぞれが単独で、または連帯して住宅ローン全額に対する返済義務を負っています。どちらか一方でもローンの返済を滞納すると、金融機関は連帯保証人であるもう一方に対して残債全額の一括返済を求めることになります。
もし、夫婦ともにローンを返済できなくなった場合、金融機関は担保となっている不動産を差し押さえ、最終的には裁判所の管理下で「競売」にかけて強制的に売却し、貸付金の回収を図ります。競売は市場価格よりも大幅に低い価格で売却されることが多く、その後の残債務が多額になるリスクが高いです。ローン返済が困難になった際は、競売になる前に任意売却などの手段を検討することが重要です。
住宅ローンの契約内容に注意:契約違反リスク
多くの住宅ローン契約には、「契約者自身が居住すること」が条件として盛り込まれています。ペアローンで購入した不動産に、夫婦の一方または双方が住まなくなった場合、これは住宅ローン契約の「居住要件」に違反することになります。
また、金融機関に無断で不動産の名義変更を行ったり、第三者に賃貸したりすることも、契約違反とみなされる行為です。これらの契約違反が金融機関に発覚した場合、期限の利益を喪失し、住宅ローンの残債全額の一括返済を二人に求められます。離婚に伴い居住状況が変わる場合は、必ず事前に金融機関に相談し、適切な手続きについて確認することが不可欠です。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
離婚時の任意売却ならセンチュリー21中央プロパティーに相談
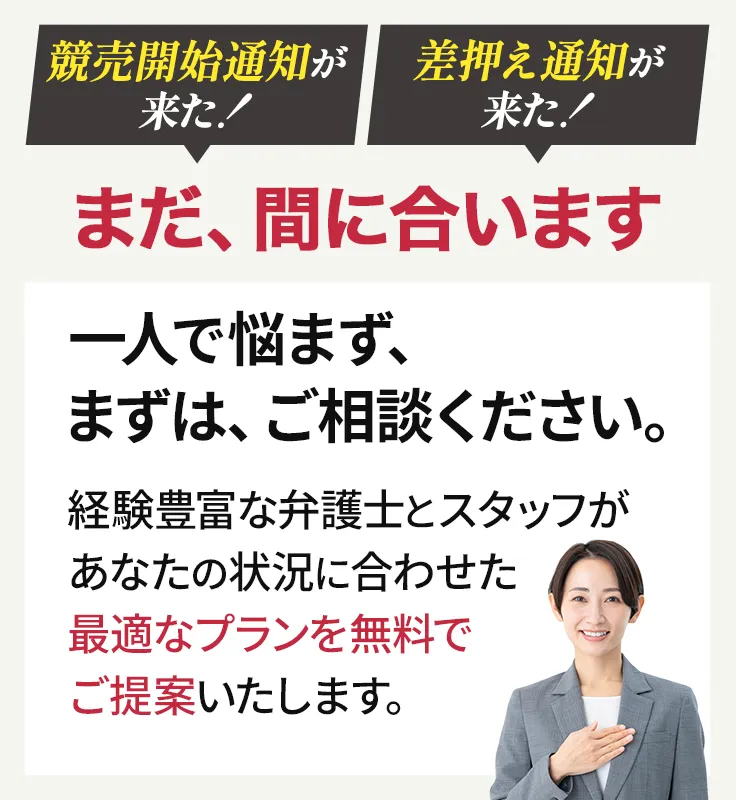
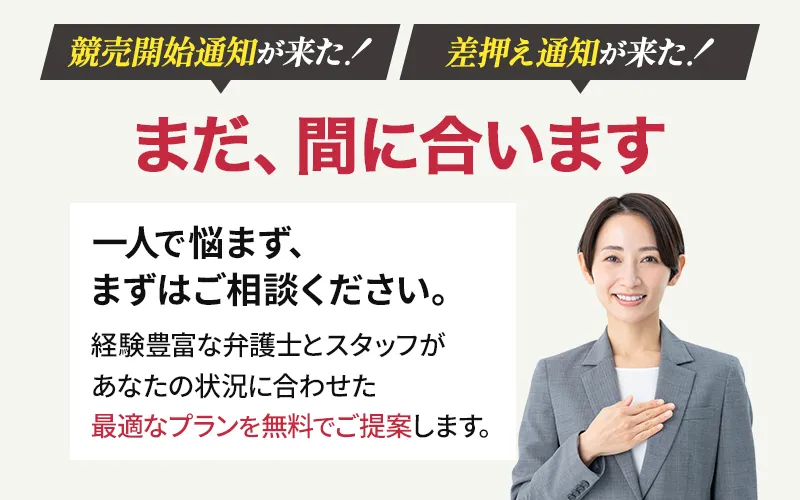
ペアローン返済中の離婚問題では、返済負担増大や維持管理の困難、売却・相続の複雑化、滞納・契約違反リスクなど、多岐にわたる深刻な問題が生じます。
主な対応策としてローンの1本化や売却が考えられますが、特にオーバーローン時の任意売却では、夫婦合意、金融機関交渉、残債処理、連帯保証継続、税金等に十分な注意が必要です。共有名義継続にもリスクが伴うため、これらの複雑な問題を円満かつ適切に解決するには、弁護士や不動産専門家への早期相談が不可欠です。
センチュリー21中央プロパティーは、任意売却に関する豊富な知識と実績を持っています。当社では、債務整理に強い常駐の社内弁護士が、債権者への交渉を行います。離婚時の任意売却についても、これまで多くのサポートを行ってきた実績があります。
弁護士相談費用や仲介手数料など、売却に伴う費用は一切ございません。住宅ローンでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


