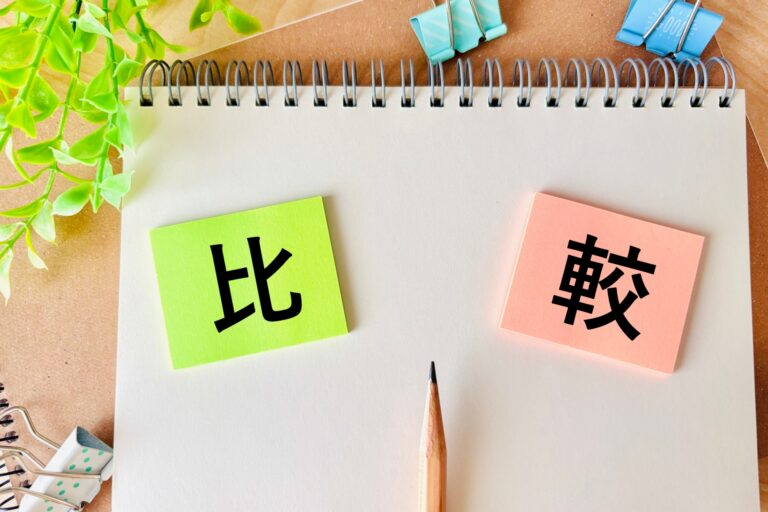任意売却と一般売却の違いは、売却に至る背景にあります。
本記事では、任意売却と一般売却の基本的な違いから、手続きの流れ、費用、そして売却にかかる期間までを徹底的に比較解説します。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
目次
任意売却と一般売却の基本的な違い
不動産の売却を検討する際、「任意売却」と「一般売却」という二つの方法があります。どちらも不動産を売却するという目的は同じですが、その背景、手続き、そして関係者に大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの基本的な概念と、両者の根本的な違いを分かりやすく解説します。
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ってしまい、このままでは競売にかけられる可能性が高い場合に、債務者(家の所有者)が債権者である金融機関(銀行や信用金庫など)の同意を得て、不動産を市場で売却する方法です。
競売も住宅ローンが返済できなくなった不動産が売却される手続きですが、裁判所が主導で行い、市場価格よりも大幅に低い価格で落札されることが多いのが特徴です。
一方、任意売却は、債務者が主体的に不動産業者を選び、市場価格に近い価格で売却を目指すことができます。これにより、競売よりも多くの売却代金を得られる可能性があり、残債務を減らすことができる、精神的な負担が競売よりも少ないといったメリットが期待できます。
一般売却とは
一般売却とは、住宅ローンに滞納がない場合や、既に完済している場合に、売主自身の意思に基づいて自由に不動産を売却する方法です。売主は、自身の希望する時期や価格で、仲介業者を選び、市場で買い手を探すことができます。
一般売却では、まず不動産業者に査定を依頼し、売却価格を決定します。その後、不動産業者と媒介契約を結び、広告活動や内覧などを通じて買い手を探します。買い手が見つかれば、価格や引き渡し条件などを交渉し、売買契約を締結、決済・引き渡しという流れになります。
| 任意売却 | 一般売却 | |
| 売却の主導権 | 債務者(ただし、債権者の同意が必須) | 売主 |
| 債権者の関与 | 金融機関の同意・交渉が不可欠 | 原則として不要 |
| 売却理由や背景 | 住宅ローン滞納、競売回避 | 住み替え、転勤、資産整理など売主の自由な意思 |
| 売却価格 | 市場価格に近い価格を目指す | 市場価格に基づいて売主が決定 |
| 手続きの複雑さ | 債権者との交渉など、一般売却より複雑 | 一般的な不動産売買手続き |
| 時間的な制約 | 定められた競売手続きの期限がある | 売主のペースで進められる |
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
任意売却と一般売却の流れの違い
不動産を売却する際、任意売却と一般売却では、その手続きの流れが大きく異なります。
ここでは、任意売却と一般売却の具体的な流れを比較しながら詳しく解説します。
任意売却の流れ
任意売却は、住宅ローンの滞納によって進められる、競売という最終手段を避けるために選択する手続きです。そのため、その流れも一般的な不動産売却とは異なる特有のステップを含んでいます。
- 住宅ローン滞納と専門家への相談
住宅ローンの支払いが困難になった場合、まず金融機関から督促状が届きます。この段階で放置せず、早めに任意売却に強い不動産業者や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
- 債権者(金融機関)との交渉
弁護士や不動産会社が窓口となり、金融機関と任意売却の可能性について交渉を開始します。売却価格の目安、売却条件などを協議します。金融機関の同意を得ることが、任意売却を進めるための最初の大きなステップです。
- 不動産業者との媒介契約と売却活動
金融機関の同意が得られたら、不動産業者と媒介契約を結び、物件の売却活動を開始します。一般売却と同様に、ポータルサイトへの掲載や不動産会社独自のネットワークを通じて、販売活動が行われます。
ただし、売却価格は金融機関との協議によって決定されるため、売主の自由な裁量とは限りません。
- 購入希望者との交渉と売買契約
購入希望者が見つかれば、価格や引き渡し条件などを交渉し、合意に至れば売買契約を締結します。この際も、最終的な契約内容は金融機関の承認を得る必要がある場合があります。
- 決済と引き渡し
買主からの売買代金が支払われ、物件の引き渡しが行われます。売却代金は、仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用を差し引いた後、住宅ローンの残債務に充当されます。残債務が売却代金を上回る場合は、金融機関との間で残債の扱いについて協議することになります。
また、任意売却は、競売の開始決定がされる前に行うことが望ましいです。競売の手続きが進行してしまうと、任意売却の交渉が難航したり、期限が迫られたりする可能性があります。早期に専門家に相談し、迅速に手続きを進めることが、より有利な条件での売却につながります。
一般売却の流れ
一般売却は、任意売却とは異なり、売主が自身の意思に基づいて、比較的自由に手続きを進めることができる売却方法です。
- 売却準備(査定、仲介業者選定)
まず、複数の不動産業者に査定を依頼し、物件の適正な市場価格を把握します。その上で、信頼できる仲介業者を選び、媒介契約を結びます。媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があり、売却活動の進め方や業者の責任範囲などが異なります。
- 媒介契約
選定した不動産業者と媒介契約を結び、正式に売却活動を依頼します。媒介契約書には、売却価格、契約期間、仲介手数料などが記載されます。
- 売却活動
不動産業者は、インターネット広告への掲載、不動産情報誌への掲載、現地販売の開催など、様々な方法で物件の購入希望者を探します。
- 内覧
購入希望者が現れた場合、事前に日程調整を行い、物件の内覧を実施します。売主は、部屋を綺麗に掃除・整頓し、良い印象を与えられるように準備することが重要です。
- 購入申し込みと条件交渉
購入希望者から購入の申し込みが入ると、価格や引き渡し時期などの条件交渉を行います。売主は、自身の希望を踏まえつつ、買主との合意を目指します。
- 売買契約
条件交渉がまとまれば、売買契約を締結します。契約書には、売買価格、手付金の額、引き渡し時期、特約事項などが記載されます。
- 決済と引き渡し
買主から残りの代金が支払われ、物件の鍵や関係書類を引き渡します。同時に、抵当権の抹消手続きなどが行われます。
一般売却では、売主が売却価格を決定したり、内覧のスケジュールを調整したり、購入希望者との条件交渉を行ったりする際に、比較的大きな裁量権を持つことができます。
一方、任意売却では、これらの決定に金融機関の意向が強く影響するため、売主の自由度は低くなります。
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
任意売却と一般売却にかかる費用の違い
不動産を売却する際、任意売却と一般売却では、発生する費用とその負担方法に違いがあります。
ここでは、任意売却と一般売却にかかる費用を詳しく比較検討してみましょう。
任意売却にかかる費用
任意売却では、売却によって得られた代金から、以下の諸費用が差し引かれることが一般的です。自己資金が少ない状況で任意売却を選択する場合、これらの費用を事前に用意する必要がないという側面があります。
- 仲介手数料
不動産業者に支払う手数料で、宅地建物取引業法によって上限が定められています。売買価格に応じて計算され、成功報酬として支払われます。一般売却と同様に発生しますが、任意売却の場合は、売却代金の中から支払われることが多いです。
- 抵当権抹消費用
住宅ローンを担保するために不動産に設定されている抵当権を抹消するための費用です。司法書士への依頼費用や登録免許税などが含まれます。一般売却と同様に発生しますが、任意売却では、売却代金から優先的に支払われるよう債権者と交渉することがあります。
- 引っ越し費用
売却後の住居への引っ越しにかかる費用です。これは一般売却と同様に、売主が負担する必要があります。ただし、自己資金が乏しい場合は、売却代金から一部を捻出できるよう債権者と交渉する余地がある場合もあります。
- 滞納分の税金・管理費など(場合による)
固定資産税や都市計画税、マンションの管理費や修繕積立金などを滞納している場合、売却代金からこれらの滞納分を支払う必要が生じることがあります。債権者との交渉次第で、一部を免除してもらえる可能性もありますが、基本的には支払うべき費用となります。
- その他費用(場合による)
残置物の処分費用、ハウスクリーニング費用などが、売却代金から差し引かれることもあります。これらは買主との交渉や債権者の意向によって扱いが変わります。
任意売却を選択する理由の一つに、住宅ローンの返済が滞っているなど、経済的に困窮している状況が挙げられます。
そのため、上記のような費用を事前に用意することが難しいケースも少なくありません。このような場合、不動産業者を通じて債権者と交渉し、売却代金の中からこれらの費用を支払えるように調整することが重要になります。債権者も、競売よりも任意売却の方が回収額が多くなる可能性があるため、合理的な範囲であれば費用の捻出に協力してくれることがあります。
一般売却にかかる費用
一般売却では、不動産の売却によって得られた利益(売却代金から購入時の価格や諸費用を差し引いたもの)の中から、以下の費用を支払うのが一般的です。
- 仲介手数料
任意売却と同様に、不動産仲介業者に支払う手数料です。売買契約が成立した際に、成功報酬として支払われます。
- 抵当権抹消費用
住宅ローンが残っている場合は、抵当権を抹消するための費用がかかります。司法書士への依頼費用や登録免許税などが含まれます。
- 引っ越し費用
新居への引っ越しにかかる費用は、売主が自己負担します。
- ハウスクリーニング費用(場合による)
より良い条件で売却するために、売主の判断でハウスクリーニングを行うことがあります。この費用は売主が負担します。
- その他費用(場合による)
不動産の状況によっては、測量費用や建物診断費用などがかかることがあります。これらは売主の判断で発生します。
一般売却では、売却によって利益が出ることが前提となるため、これらの費用は売却代金から諸費用を差し引いた残りの金額から支払うのが一般的です。
| 費用 | 任意売却 | 一般売却 |
| 仲介手数料 | 売却代金から差し引かれる | 売却代金から支払う |
| 抵当権抹消費用 | 売却代金から優先的に支払われるのが一般的 | 自己負担 |
| 引っ越し費用 | 自己負担が原則だが、売却代金からの捻出を交渉する場合がある | 自己負担 |
| 滞納分の税金・管理費 | 売却代金から優先的に支払う | 通常は売却益とは別に支払う |
| ハウスクリーニング費用 | 売却代金から差し引かれる | 売主と買主で協議 |
| 自己資金の必要性 | 比較的少ない(交渉次第で、売却代金から費用を捻出できる場合がある) | ある程度必要 |
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
任意売却と一般売却にかかる期間の違い
任意売却と一般売却では、手続きの性質上、売却にかかる期間に大きな違いが見られます。ここでは、それぞれの期間について詳しく解説し、比較検討してみましょう。
任意売却にかかる期間
任意売却は、住宅ローンの滞納という背景があり、債権者である金融機関との交渉が不可欠となるため、一般売却と比較して期間が読みにくい側面があります。
また、競売の期日が迫っている場合は、時間的な制約を受けるため迅速な手続きが必要です。
- 債権者との交渉期間
任意売却を進めるにあたり、まず金融機関にその意向を伝え、同意を得る必要があります。この交渉期間は、金融機関の担当部署や内部手続き、担保不動産の状況などによって大きく変動します。
スムーズに進めば数週間で済むこともありますが、条件交渉が難航したり、複数の債権者がいる場合は数ヶ月を要することもあります。
- 売却活動期間
金融機関の同意が得られた後、不動産業者と媒介契約を結び、売却活動を開始します。この期間は、一般売却と同様に、物件の価格設定、市場動向、物件の魅力度などによって左右されます。
ただし、任意売却の場合は、金融機関が設定する最低売却価格(債権回収の目安)があります。そのため、買い手が見つからないからといって、すぐに売却価格を下げることができず、都度債権者への確認と交渉が必要です。交渉が難航した場合、売却活動が長期化する可能性もあります。一般的には、3ヶ月~6ヶ月程度を目安とすることが多いです。
- 契約・決済までの期間
買い手が見つかり、売買契約を締結した後、決済・引き渡しまでの期間は、一般売却と大きく変わりません。通常、1ヶ月~2ヶ月程度で完了します。ただし、任意売却の場合は、最終的な契約内容や決済についても金融機関の承認が必要となる場合があり、若干時間がかかることもあります。
任意売却を行う上で最も重要なのは、競売の期日を意識することです。競売の開始決定通知が届いてしまうと、任意売却の交渉が難しくなり、時間的な猶予も少なくなります。競売の開札日前日までに任意売却を成立させる必要があるため、住宅ローンの滞納が始まったら、できるだけ早く専門家に相談し、迅速に手続きを進めることが重要です。
一般売却にかかる期間
一般売却は、売主自身の意思に基づいて進めることができるため、任意売却と比較して、ある程度売主のペースで進めやすいと言えます。しかし、売却期間は市場の状況や物件の条件によって大きく変動します。
- 売却準備期間
複数の不動産業者に査定を依頼したり、仲介業者を選定したりする期間です。通常、数週間程度で完了します。
- 媒介契約期間
不動産業者と媒介契約を結んでから、本格的な売却活動を開始するまでの期間です。契約内容の確認などに数日かかることがあります。
- 売却活動期間
物件を市場に公開し、購入希望者を探す期間です。この期間は、物件の価格設定、立地、築年数、状態、市場の需給バランスなどによって大きく変動します。人気のある物件であれば短期間で買い手が見つかることもありますが、そうでない場合は数ヶ月、あるいは半年以上かかることもあります。一般的には、3ヶ月程度を目安とすることが多いです。
- 内覧期間
売却活動期間中に、複数の購入希望者が内覧に訪れます。内覧の頻度や期間は、物件への関心度によって変わります。
- 契約・決済までの期間
購入希望者から購入の申し込みがあり、価格や条件交渉がまとまって売買契約を締結した後、通常1ヶ月~2ヶ月程度で決済・引き渡しが行われます。
一般売却では、売主が希望する売却価格や条件をある程度設定でき、内覧のスケジュールなども自身の都合に合わせて調整しやすいというメリットがあります。
しかし、買い手が見つかるまでの期間は市場の状況に大きく左右されるため、売主の希望通りに短期間で売却できるとは限りません。
| ステップ | 任意売却 | 一般売却 |
| 債権者との交渉 | 数週間~数ヶ月 | 不要 |
| 売却活動 | 3ヶ月~6ヶ月程度(物件による) | 3ヶ月程度(物件による、長期化も) |
| 内覧 | 売却活動期間に含む | 売却活動期間に含む |
| 契約・決済 | 1ヶ月~2ヶ月程度(債権者の承認による遅延の可能性あり) | 1ヶ月~2ヶ月程度 |
【実績5,000件以上】不動産会社×弁護士が任意売却をサポート! ≫
住宅ローンの返済でお困りなら任意売却を検討しよう
任意売却と一般売却の最大の違いは、売却に至る背景です。
任意売却は、住宅ローンの返済ができなくなった場合に有効な手段ですが、一般売却とは異なり、債権者への交渉が必要なため、通常の売却よりも専門的なテクニックが必要です。
センチュリー21中央プロパティーは、任意売却に関する豊富な知識と実績を持っています。当社では、債務整理に強い常駐の社内弁護士が、債権者への交渉を行います。弁護士だからこそできる圧倒的な交渉力で、期限までに確実な任意売却を実現します。
弁護士相談費用や仲介手数料など、売却に伴う費用は一切ございません。住宅ローンでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。